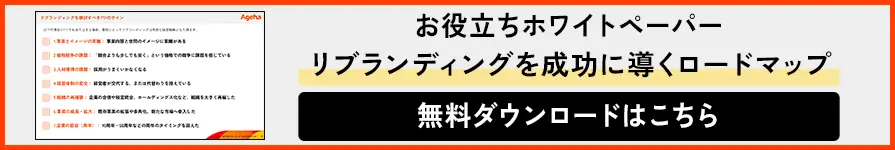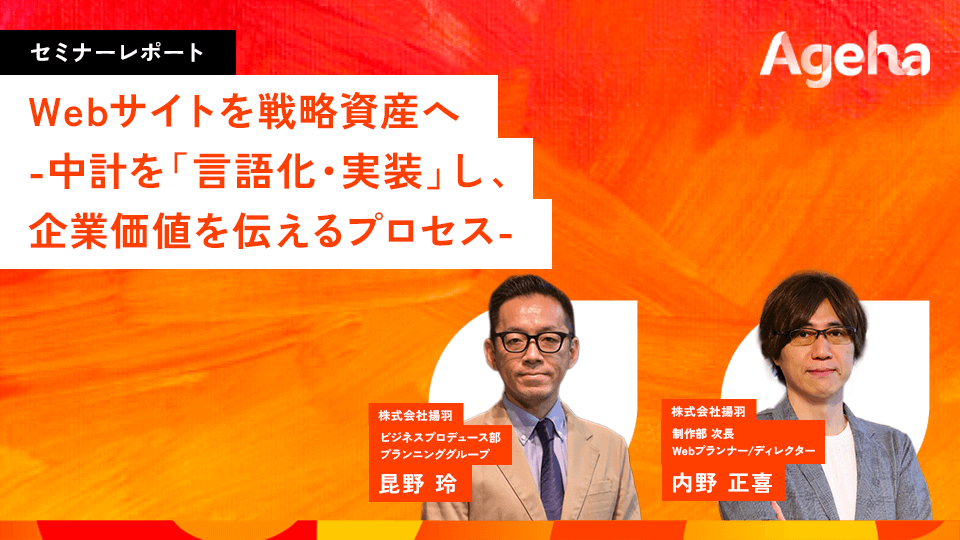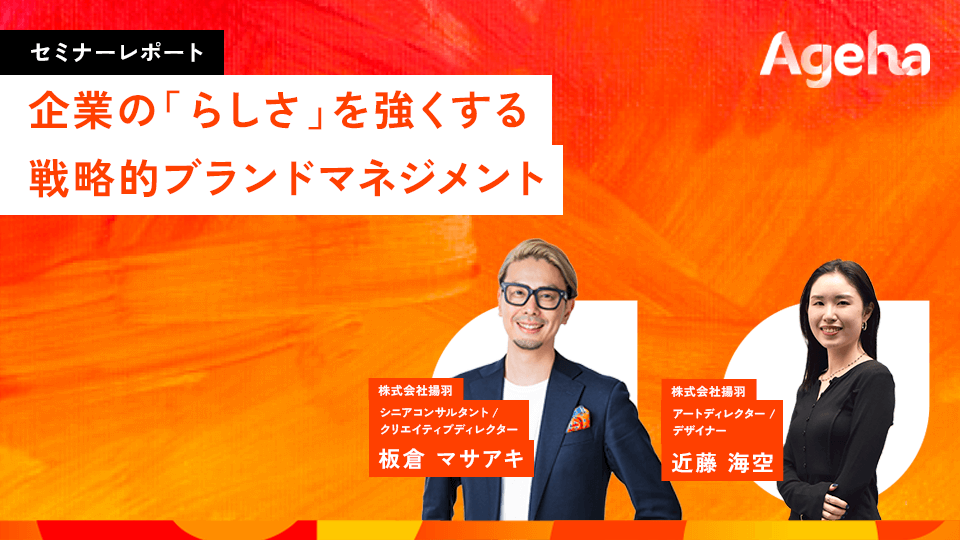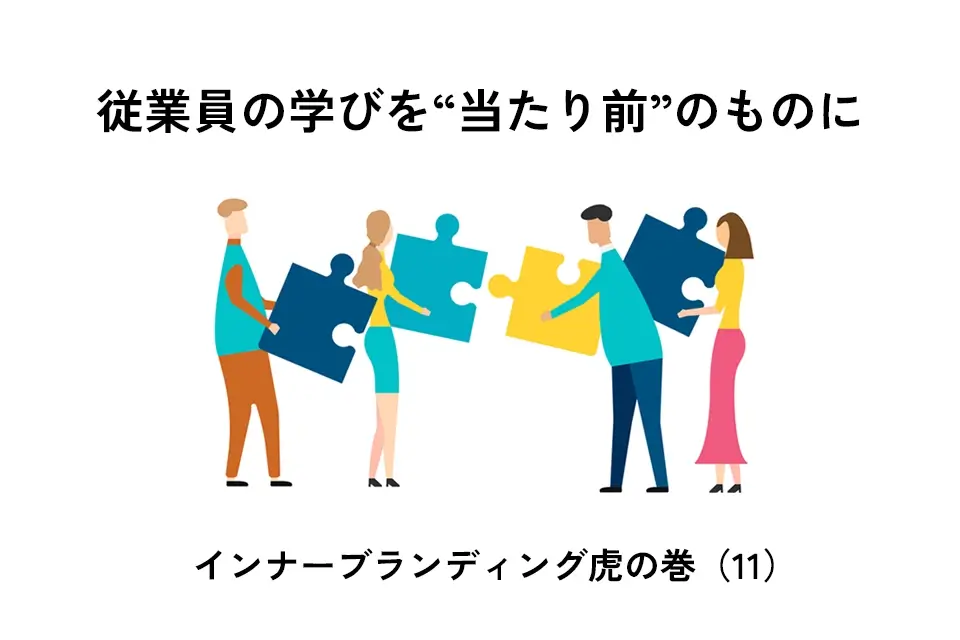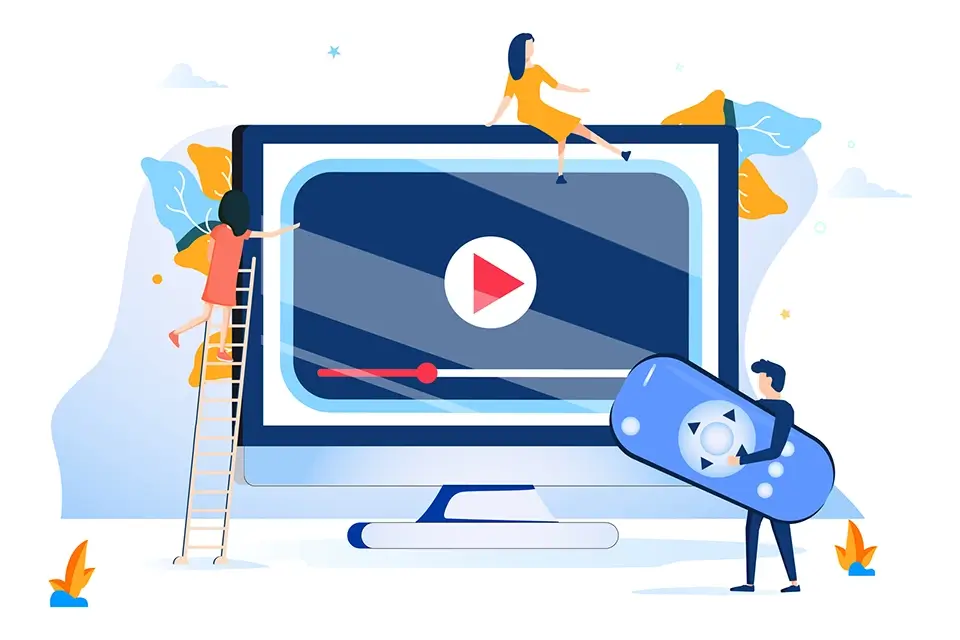「事業内容は進化したのに、世間のイメージが追い付いていない」
「競合は新しいブランド戦略で成長しているが、自社はどうだろうか」
企業を取り巻く環境が目まぐるしく変化する現代、多くの経営者や事業担当者がこうした課題意識を抱えています。その解決策として注目されるのが「リブランディング」です。
しかし、「リブランディング」という言葉は知っていても、「単にロゴを変えることと何が違うのか」、「具体的に何から手をつければいいかわからない」、「失敗するケースも多いと聞くので、リスクが気になる」といった理由で、具体的な一歩を踏出せずにいる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、リブランディングの全体像を体系的に解説します。
- 第1章:そもそも、何のためにするのか(目的:Why)
- 第2章:では、何をすればいいのか(進め方:How)
- 第3章:失敗しないための3つの鉄則(成功の秘訣:Tips)
関連記事はこちら:リブランディングの成功事例4選!目的と具体的な方法を解説
第1章:リブランディングって「何のために」するの? (Why)
リブランディングの定義
まず、リブランディングとは、「既存のブランドイメージの変更・改善」を指します。既に確立されているブランドを時代のニーズに合わせて改善・変革するためのブランディング手法です。
市場の変化が加速し、顧客の価値観が多様化する現代において、どんなに優れたブランドでも、何もしなければその価値は時代とともに陳腐化してしまいます。
そのため、リブランディングは単なるイメージチェンジではなく、企業の経営課題を解決し、未来の成長を描くための重要な「ビジネス戦略」なのです。
では、具体的にどのような目的で実施されるのでしょうか。
1. 事業成長を加速させるため(攻めのリブランディング)
現状の事業基盤に安住するのではなく、未来の成長機会を積極的に掴むためにリブランディングを行うのが「攻めのリブランディング」です。市場での競争優位性を確立し、新たな顧客層や事業領域へと拡大していくための強力な推進力となります。
これは、自社のポジショニングを再定義し、事業の可能性を広げるための戦略的な一手と言えます。
・事業の成長・拡大・変化への対応
既存事業の拡張や多角化、新たな市場への参入といったビジネス環境の変化に対応するために実施されます。これにより、競合との差別化を図り、市場でのポジショニングを見直すことができます。
・提供価値の再定義と高付加価値化
企業の成長に伴い、「モノを売る」だけでなく「ソリューションを提供する」など、提供価値が進化することがあります。リブランディングによって現在の価値を正しく伝えることで、価格競争から脱却し、収益構造の変革を目指します。
2.時代への適応と課題解決のため(守りのリブランディング)
時代の変化や内部環境の変化によって生じた課題に対応し、事業基盤を再強化することが「守りのリブランディング」の目的です。ブランドイメージが現状の事業内容と合わなくなったり、時代遅れになったりした場合に、その価値を現代のニーズに合わせて修正します。経営体制の変更や事業再編といった大きな節目を乗り越え、ブランドの持続可能性を確保するためにも不可欠な取り組みです。
・ブランドイメージの陳腐化・老朽化の刷新
時代遅れになったブランドイメージを現代のニーズに合わせて刷新し、ブランドを活性化させます。
・経営体制の変化への対応
経営者の交代は、新しいビジョンを掲げリブランディングを行う良い機会となります。また、企業の合併や経営統合といった事業再編の際には、異なる企業文化をすり合わせ、新たなブランドイメージを訴求する必要があります。
・ネガティブイメージの払拭と信頼回復
不祥事などによって傷ついたブランドイメージを回復し、「生まれ変わる」という強い決意を社会に示すために実施されることもあります。
・周年を契機とした未来への姿勢の訴求
周年は企業の転換期と捉えられ、歴史を振り返りつつ、未来への姿勢を社内外に示す効果的なタイミングとなります。
3.組織(社内)を強くするため(インナーブランディング)
リブランディングの成否を最終的に左右するのは、顧客や市場といった「外側」への発信だけではありません。むしろ、社員という「内側」への浸透こそが、ブランドの価値を確かなものにし、持続的な成長の基盤を創ります。
どんなに優れた戦略やデザインも、それを実行する社員の理解と共感がなければ実態の伴わないものになってしまいます。そのため、組織全体で一貫したブランド体験を提供するためのインナーブランディングは、重要な目的の一つです。
・社員のエンゲージメントと誇りの醸成
プロセスを通じて企業の存在意義やビジョンを再確認・共有することで、社員の仕事への誇りと貢献意欲を高めます。
・採用競争力の強化
企業のビジョンやカルチャーを明確に打ち出すことで、それに共感する優秀な人材を引き寄せ、採用のミスマッチを減らす効果も期待できます。
第2章:リブランディングって「何を」すればいいの? (How)
リブランディングの目的が明確になったら、次はその目的を達成するための具体的な実行フェーズに移ります。成功するリブランディングは、思いつきや個人のセンスで進められるものではなく、体系立てられたプロセスに沿って進めることが重要です。
ここでは、プロジェクトを成功に導くための普遍的かつ重要なプロセスを、5つのステップに分けて解説します。分析から始まり、アイデンティティの定義、クリエイティブ開発、そして浸透・育成へと続くこの手順は、プロジェクトを着実に進めるための重要な指針となります。
ステップ1:【体制構築と現状分析】推進チームを発足し、現在地を知る
まず、社長や経営層だけでなく、部署を横断した責任者や有志による「ブランド推進チーム」を発足させます。これにより、全社的な合意形成と現場への浸透がスムーズになります。
次に、客観的なデータに基づいて自社の立ち位置を把握します。
・調査・分析
顧客調査や従業員インタビューを実施し、競合分析を行います。その際、売上などの定量データと、ブランドへの想いといった定性データを組み合わせて分析することが重要です。
・ゴールの具体化
分析結果に基づき、リブランディングの目的を測定可能なゴール(KGI/KPI)に落とし込みます。
ステップ2:【ブランド・アイデンティティ定義】ブランドの「揺るぎない核」を言語化する
ここがリブランディングの根幹をなす部分です。分析結果を踏まえ、自社ブランドが「何者であり、どこへ向かうのか」という根本的なアイデンティティ(自己認識)を、明確な言葉で定義します。
・提供価値の洗い出しと深掘り
現在のブランド価値を洗い出し、社長や役員へのインタビュー調査を通じて、企業の信念などのキーワードを深堀りします。
・ブランドストラクチャーの作成
深堀りした情報を整理・構造化し、「ブランドストラクチャー」を作成することで、ブランドが顧客や社会に与える提供価値(コアバリュー)、情緒的価値、機能的価値などを明確にします。
・アイデンティティの言語化
明確になったコアバリューをもとに、ミッション(存在意義)、ビジョン(目指す未来)、バリュー(価値観・行動指針)を定義します。この過程では、全社員アンケートやワークショップを実施し、社員を巻き込むことが強固なブランド形成に繋がります。
ステップ3:【クリエイティブ開発】ブランドの「核」を目に見える形に落とし込む
言語化された理念や価値観を、具体的なデザインや言葉に落とし込んでいく創造的なプロセスです。この時、既存のブランド資産を活かしつつ、変えるべき点と維持すべき点を見極めることが重要です。
・言語要素(バーバル・アイデンティティ)
社名、ブランドスローガン、ブランドストーリーなどを開発します。
・視覚要素(ビジュアル・アイデンティティ)
ブランドロゴ、ブランドカラー、フォントなどを開発します。
・各種ツールへの展開
Webサイト、会社案内、名刺、広告など、顧客とのあらゆる接点で一貫したブランドイメージを設計します。
ステップ4:【ローンチ(発表)】社内外へ、新しいブランドを戦略的に展開する
新しいブランドを世に送り出すステップです。しかし、成功のためには周到な準備にかかっています。
・インナーローンチ(社内発表)
社外に発表する前に、必ず社員に対してお披露目の場を設けます。リブランディングの理由や新しく込めた想いについて、経営トップ自らの言葉で想いを語り、社員が新ブランドの「第一のファン」となることを目指します。
・アウターローンチ(社外発表)
プレスリリースやWebサイト、SNSなど複数のチャネルを連動させ、顧客、取引先、株主などに向けて一斉に発信します。説明動画などのデジタルチャネルの活用は、認知スピードを向上させる効果があります。
ステップ5:【浸透・育成】ブランドを守り、育て、改善を続ける
発表はゴールではなく、スタートです。リブランディングが形骸化して終わらないよう、育てていく施策が必要です。
・ブランドガイドラインの策定と運用
ロゴの使い方や色の規定など、ブランドの一貫性を保つためのルールブックを作成し、全社員や協力会社と共有します。あらゆるタッチポイントで一貫したイメージを保つことで、その価値が蓄積されていきます。
・一貫したコミュニケーション
インナーブランディングとアウターブランディングを両輪で実行し、社内外に一貫したブランドメッセージを発信し続けることが不可欠です。
・効果測定と改善
リブランディング後は、3ヶ月、6ヶ月、1年単位で定期的に効果を測定し、目標とのズレがあれば軌道修正を行います。
・組織文化への醸成
最終的にブランドを形つくるのは「人」です。社員一人ひとりが新しいブランドの価値観を体現できるよう、評価制度や研修制度を見直すなど、組織文化レベルでの浸透を図ります。
第3章:失敗しないための3つの鉄則(成功の秘訣:Tips)
これまでの章で、リブランディングの目的(Why)と具体的な進め方(How)を見てきました。しかし、ただ手順通りにプロジェクトを進めるだけでは、大きな成功を収めることは困難です。リブランディングは、多くの部署や人々が関わる複雑な活動だからこそ、その成否を分ける普遍的な「原則」が存在します。
最後に、各ステップの土台となり、プロジェクト全体を成功に導くために重要な「3つの心構え」をご紹介します。
鉄則1:リブランディングは「経営の意志決定」そのものである
第2章で推進チームの発足を述べましたが、これは担当部署に任せきりで良いという意味ではありません。リブランディングは、会社の未来を左右する「全社的な経営改革」です。
部門間の利害調整や、ブランドの核となる理念の最終的な承認など、経営トップにしか下せない重い「意思決定」が数多く存在します。経営者がこのプロジェクトを自らの最重要任務として捉え、リーダーシップを発揮することが成功の鍵となります。
鉄則2:ブランドは「社内」から生まれる文化である
どんなに優れたブランドも、日々顧客に接する社員の行動を通じて体現されていなければ、それは実態の伴わないものになります。社員一人ひとりがブランドの価値を深く理解し、自らの行動に反映させていく体現者となることが重要です。リブランディングとは、そのような「企業文化を再構築する活動」でもあるのです。そのための対話や働きかけを、プロジェクトの初期段階から継続的に行う必要があります。
鉄則3:ブランドは「プロジェクト」ではなく、「継続的な経営資産」である
ブランドは一度作ったら終わりではありません。市場や顧客との関係を通じて日々変化し、成長していくものです。リブランディングのプロジェクトチームが解散した後も、ブランド価値を測定し、維持・向上させていくための体制と意識が不可欠です。リブランディングは短期的な施策ではなく、企業の「価値を高め続ける経営資産」として捉え、長期的な視点で育てていくことが重要です。
まとめ
リブランディングとは、単なるイメージチェンジではありません。それは、会社の過去を尊重し、現在を見つめ直し、そして未来への方向性を定める、重要な経営戦略上の取り組みです。
時間と労力はかかりますが、企業の持続的な成長を可能にする戦略的な投資であり、適切に進めることで、売上や利益といった数字以上の価値を会社にもたらします。それは、社員のエンゲージメント向上、顧客との関係強化、そして未来へ向かうための基盤となります。
この記事が、貴社がリブランディングを成功させるための、確かな指針となれば幸いです。
弊社揚羽では、リブランディングを含めさまざまな企業ブランディング施策をご支援しています。お悩みがございましたら、支援実績が豊富な弊社に一度ご相談ください。