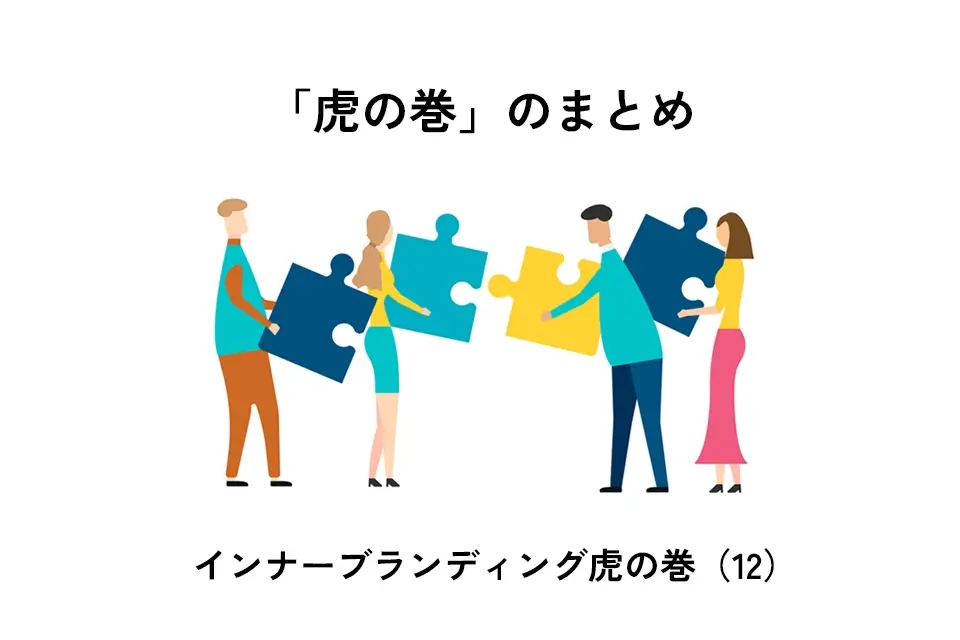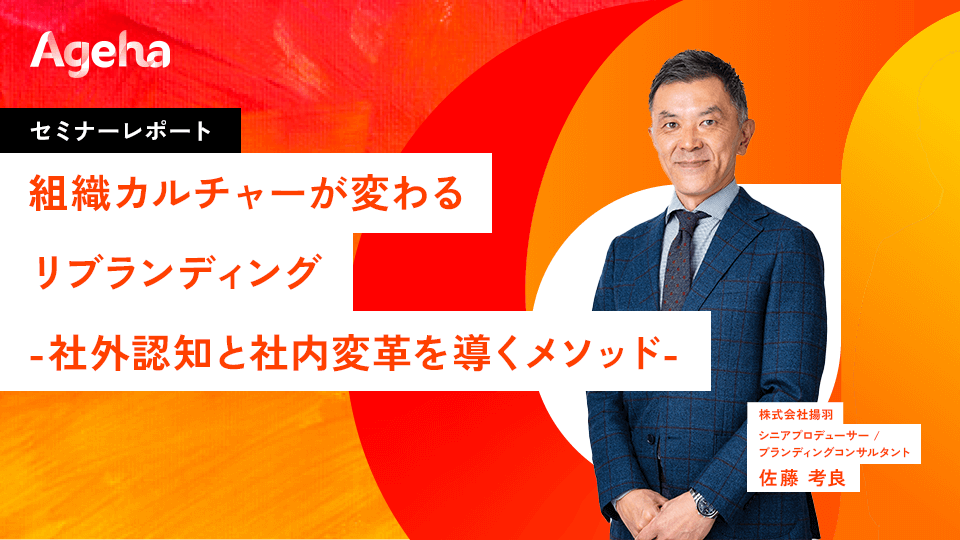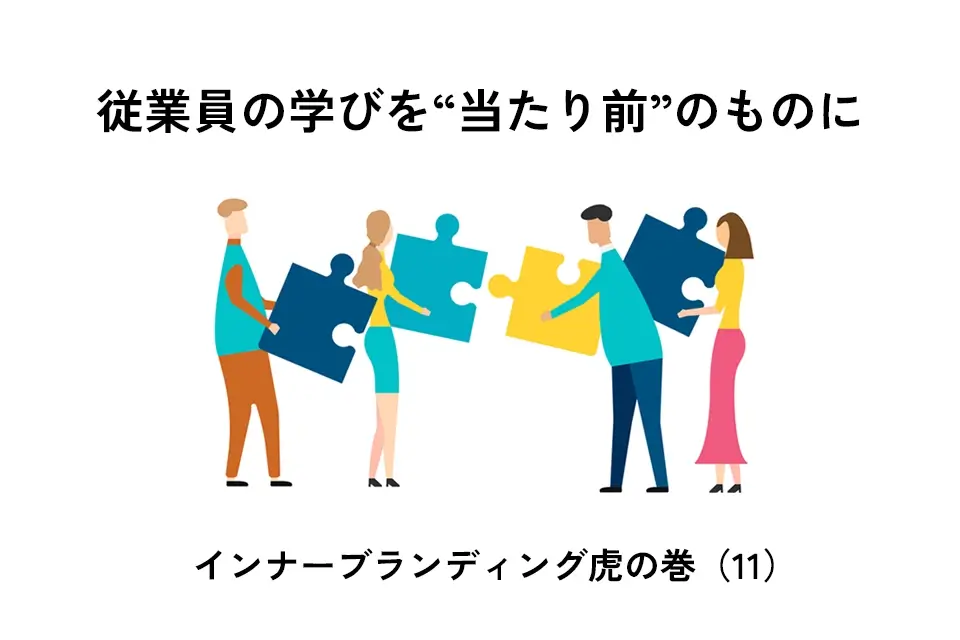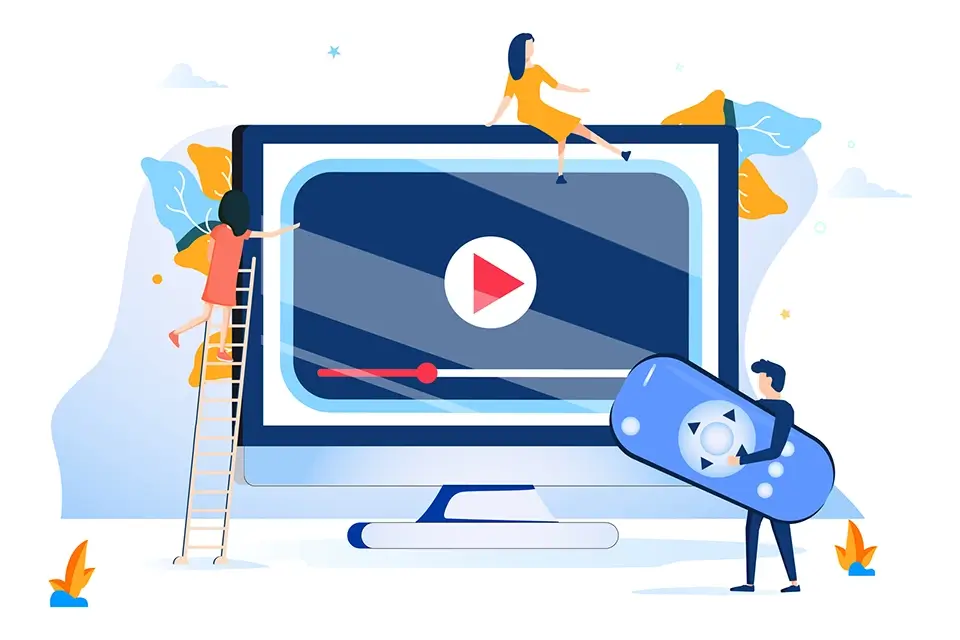理念やパーパスを明文化する企業は増えていますが、その浸透や活用において課題が残っているケースが散見されます。本稿では国内企業の実態調査を基に、企業文化を醸成し、持続的な成長を実現するためのインナーブランディングの活用法を提言します。
企業理念の明文化は、9割弱が策定済み
先にレポートした「“人的資本経営時代”におけるインナーブランディング実態調査」を通じて、国内企業において、理念やパーパスの明文化は広く進んでいる一方、浸透施策の実効性や戦略性に課題があることが明らかとなりました。
従業員への共有度やエンゲージメントへの効果実感は企業間で大きくばらつきがあり、理念が組織文化として根付いている企業は、まだまだ少数派にとどまっています。そこで本稿では、こうした現状を踏まえ、企業がインナーブランディングを推進するにあたって留意すべき点と、具体的な取り組みについて提言を行いたいと思います。
まずは「“人的資本経営時代”におけるインナーブランディング実態調査」で整理した国内企業におけるインナーブランディングの現状を再掲します。
- 理念やパーパスの明文化は、9割弱が実施済み。
- 浸透施策は実施されているものの、体系的な仕組み化には至っていない。
- 経営層の関与は限定的で、象徴的リーダーシップの不足が課題。
- 従業員の共感度は高いが、自分ごと化や共有は十分でない。
- 施策の成果実感にばらつきがあり、戦略性もまだ限定的。
インナーブランディングを経営の中核に位置づける
上記を踏まえた最初の提言は、インナーブランディングを単なる人事施策やイベントにとどめず、「経営戦略の中核に位置づける」ことです。理念やパーパスは企業の存在意義を示すものであり、事業戦略や人材戦略と密接に結び付いて初めて効果を発揮します。
例えば、人的資本経営の観点からは、従業員を「コスト」ではなく「価値を生み出す資本」として捉え、その成長と活躍を通じて企業価値を高めることが求められます。理念を戦略に埋め込み、採用、人材育成、評価制度、組織開発といったあらゆる仕組みに一貫性を持たせることが、持続的成長の基盤となります。
インナーブランディングを経営計画や中期ビジョンの中に、明確な位置づけとして組み込み、具体的な数値目標やKPI(重要業績評価指標)とひも付けることが重要です。そうすることで、単発のイベントやキャンペーンにとどまらず、日常的な業務や人材育成のプロセスにまで浸透させられます。その結果、インナーブランディングは「一過性の施策」から「企業全体の成長戦略」を支える取り組みへと発展するでしょう。
経営層が主体的なメッセージと行動で示す
第二の提言は、理念浸透において「経営層が主体的に関与する」ことです。アンケート調査では、経営層が「積極的に関与している」と回答した企業は約33%にとどまりました。その一方で、インナーブランディングの効果を「非常に感じる」企業においては、経営層の関与度が高い傾向が見られます。従業員にとって経営層の言葉や行動は、理念やパーパス浸透において、強く影響力を持つ要素になるでしょう。だからこそ経営層は、理念やパーパスを「語る人」だけではなく「体現する人」であるべきです。
全社集会や社内コミュニケーションの場で、継続的にメッセージを発信することはもちろん、自らの意思決定や日常の言動に理念を反映させることが大切です。形式的なスピーチにとどまらず、業務プロセスや人事方針に理念を織り込むことで、従業員も「経営陣は本気だ」と感じます。さらに、経営層がインナーブランディングを推進するコアリーダーになることで、管理職や中堅社員にも理念が浸透し、組織全体での一体感が醸成されるはずです。
“自分ごと化”することで、日常の行動に反映
第三の提言は、従業員への理念浸透で「“自分ごと化”するための仕組みづくり」です。アンケート回答者の9割以上は理念に共感していると回答しましたが、それが必ずしも日常の行動に反映されているとは限りません。共感を実践に変えるには、業務プロセスと理念をつなぐ仕掛けが必要です。具体的には、次のような施策が考えられます。
- 研修・ワークショップ:新入社員研修や管理職研修に理念を組み込み、行動との関連性を議論する場を設ける。
- 評価・表彰制度:理念に基づいた行動を評価基準に取り入れ、従業員のモチベーションを高める。
- 日常的なコミュニケーション:社内報やイントラネットを通じて、理念が具体的に体現された事例を紹介する。
- プロジェクトとの連動:業務プロジェクトにおいて理念をキーワードとして掲げ、意思決定や成果評価に反映する。
このように、理念を業務の中に織り込むことで、従業員は単なるスローガンとしてではなく、日常的な判断基準として理念を捉えるようになるでしょう。
可視化した成果を、社内外へ発信する
第四の提言は、「取り組みの成果を可視化し、社内外に発信する」ことです。アンケート調査では、インナーブランディングの効果を「感じる」との回答が約67%を占めたものの、「あまり感じない」とする声も約29%存在しました。効果を実感してもらうには、客観的なデータや事例を通じて、成果を示すことが不可欠でしょう。
社内に対しては、エンゲージメント調査や従業員サーベイの結果を定期的に共有し、取り組みがどのように従業員の意欲や、組織文化に影響を与えているかを示すことが有効です。成功事例や改善点を明示することで、従業員一人ひとりの取り組みが組織全体に貢献しているという実感を醸成できます。
社外に対しては、人的資本経営の情報開示が求められる中、インナーブランディングの取り組みを発信することは企業の信頼性向上につながります。投資家、求職者、顧客といったステークホルダーに対して、自社がどのように人材を大切にし、理念に基づいた経営を行っているかを伝えることは、中長期的な企業価値の向上に寄与するはずです。
成果につなげるため、新しい視点も導入する
今後のインナーブランディングにおける展望として、さらなる高度化が求められるでしょう。単に理念を「知っている」「理解している」状態から、「実践している」「成果につながっている」状態へと進化させることが重要だからです。そのためには、デジタル技術の活用や国際的な人的資本開示基準への対応など、新たな視点を取り入れる必要もでてきます。
また、多様な人材が活躍する時代においては、理念の一律的な浸透ではなく、個々人の価値観と理念の接点を探る柔軟なアプローチも欠かせません。インクルージョン(包摂)を重視したコミュニケーションや、従業員参加型の理念再定義プロセスなども有効な手法となります。
最後、繰り返しになりますが、本稿における提言は、次の4点に集約されます。
- インナーブランディングを、経営戦略の中核に位置づける。
- 理念浸透において、経営層が主体的に関与する。
- 理念やパーパスを“自分ごと化”するための仕組みづくり。
- 取り組みの成果を可視化し、社内外に発信する。
これらを適切に実践できるようになれば、インナーブランディングは単なるスローガンやイベントにとどまらず、企業文化を形成し、持続的成長を支える基盤へと進化するでしょう。人的資本経営の時代において、従業員一人ひとりが理念を自らの行動に結び付けることこそが、企業の未来を切り開く原動力となるはずです。