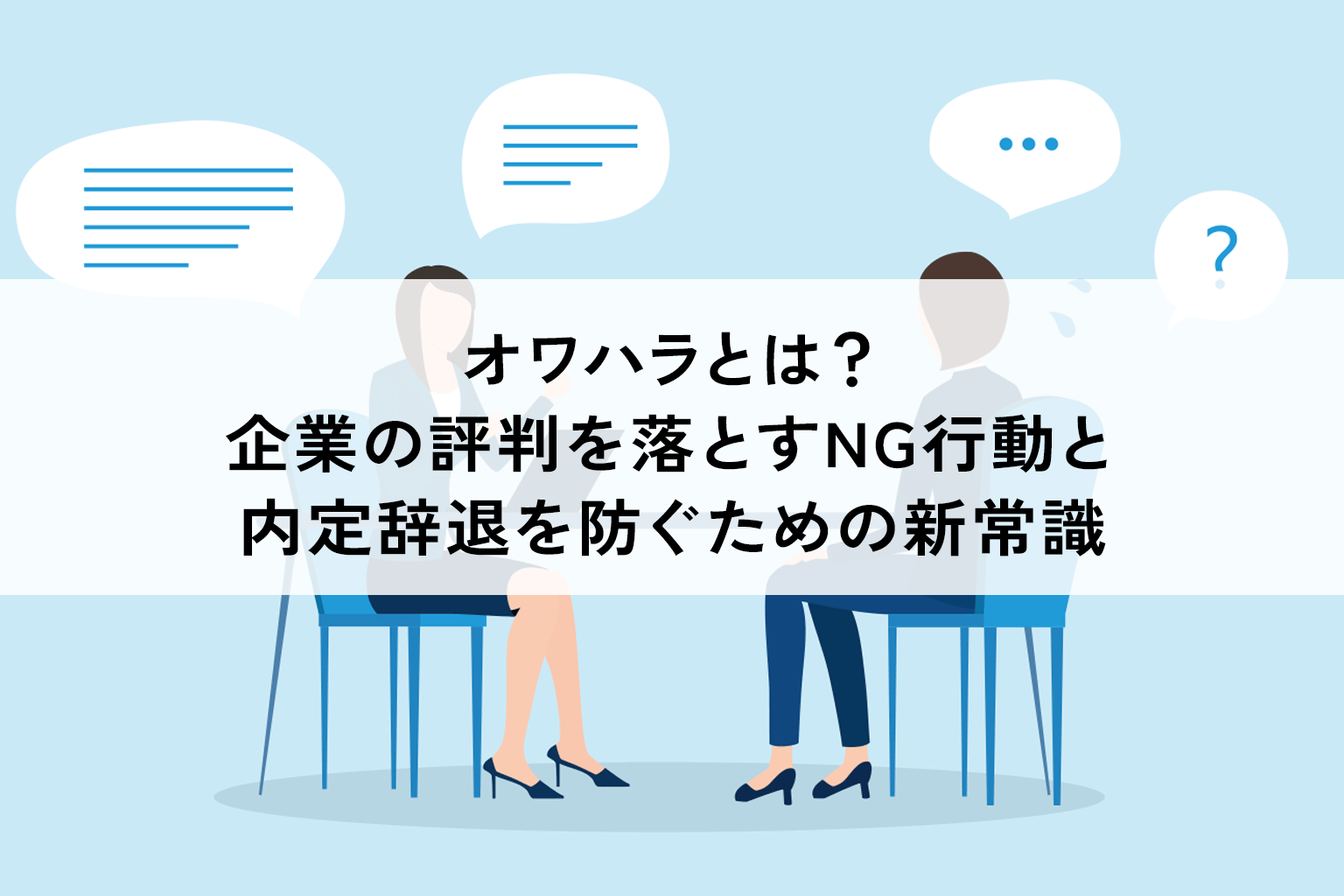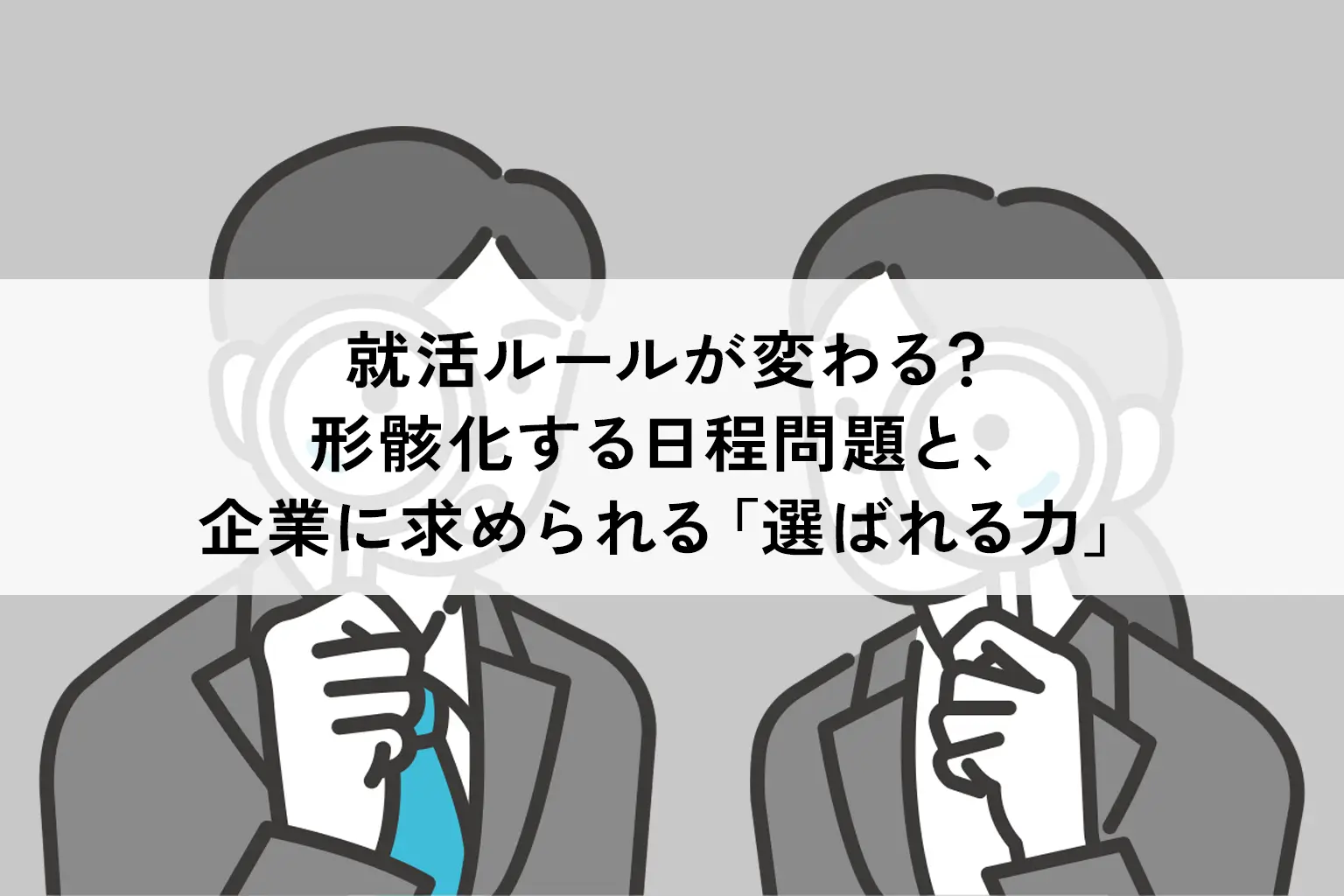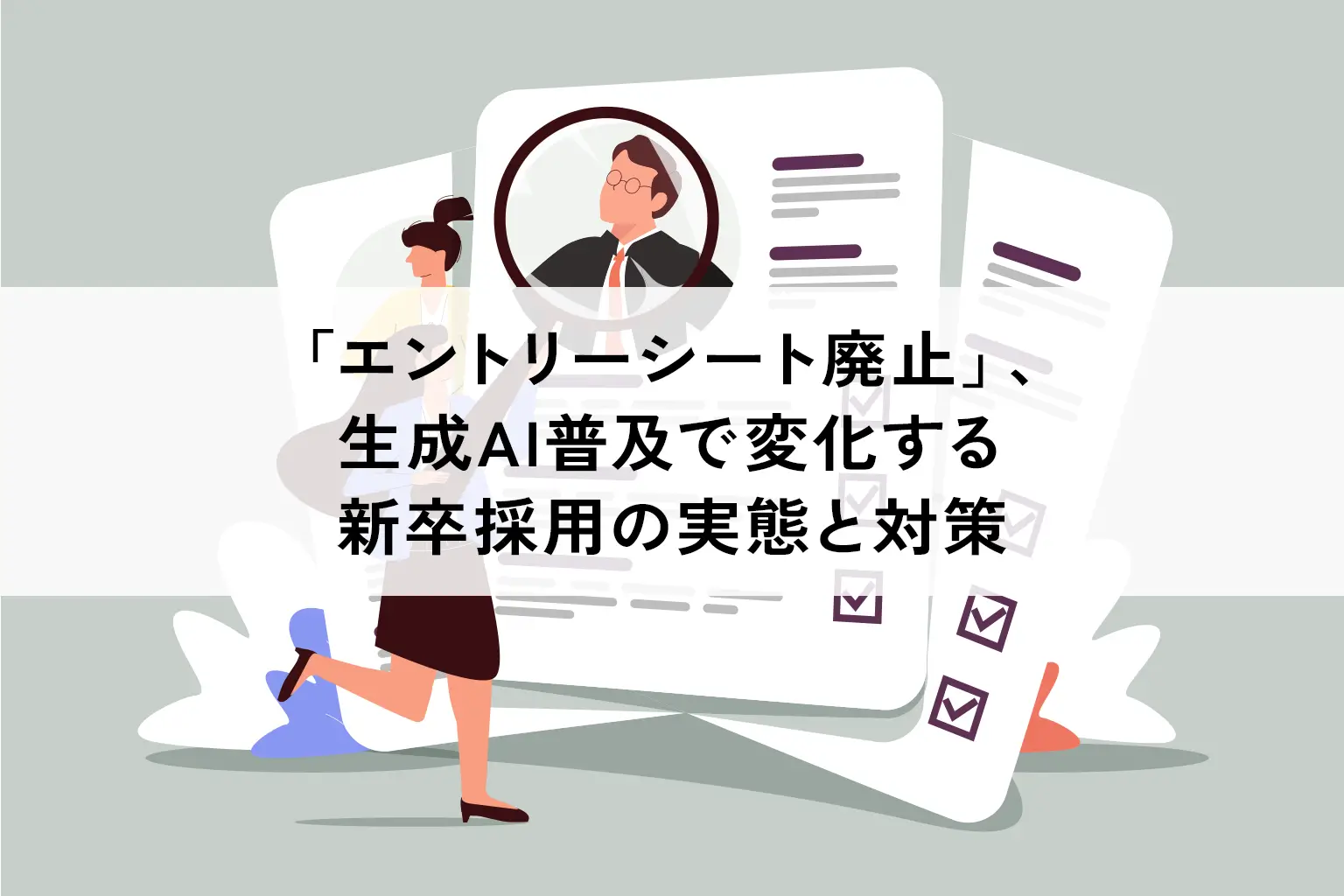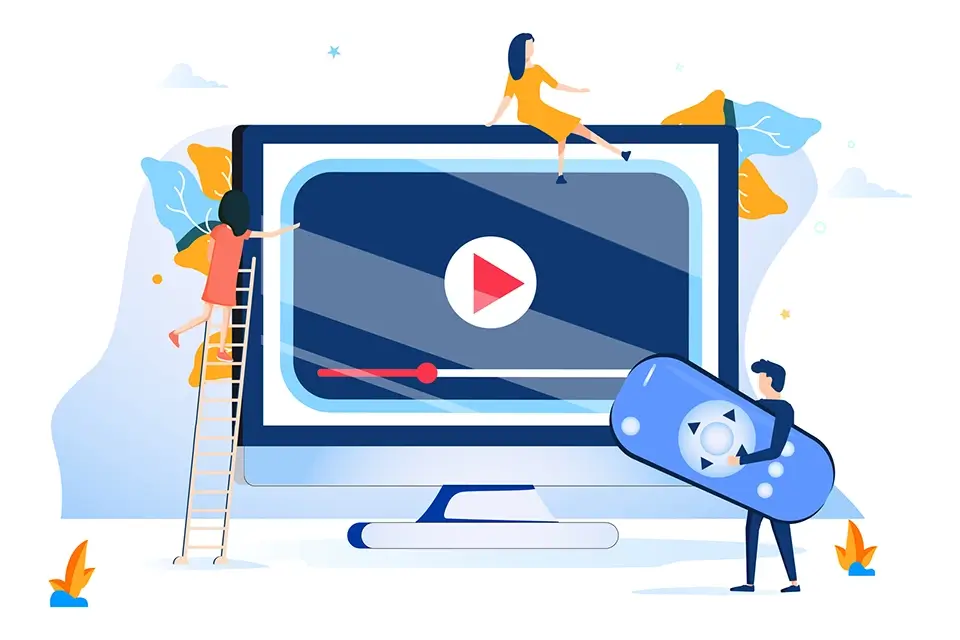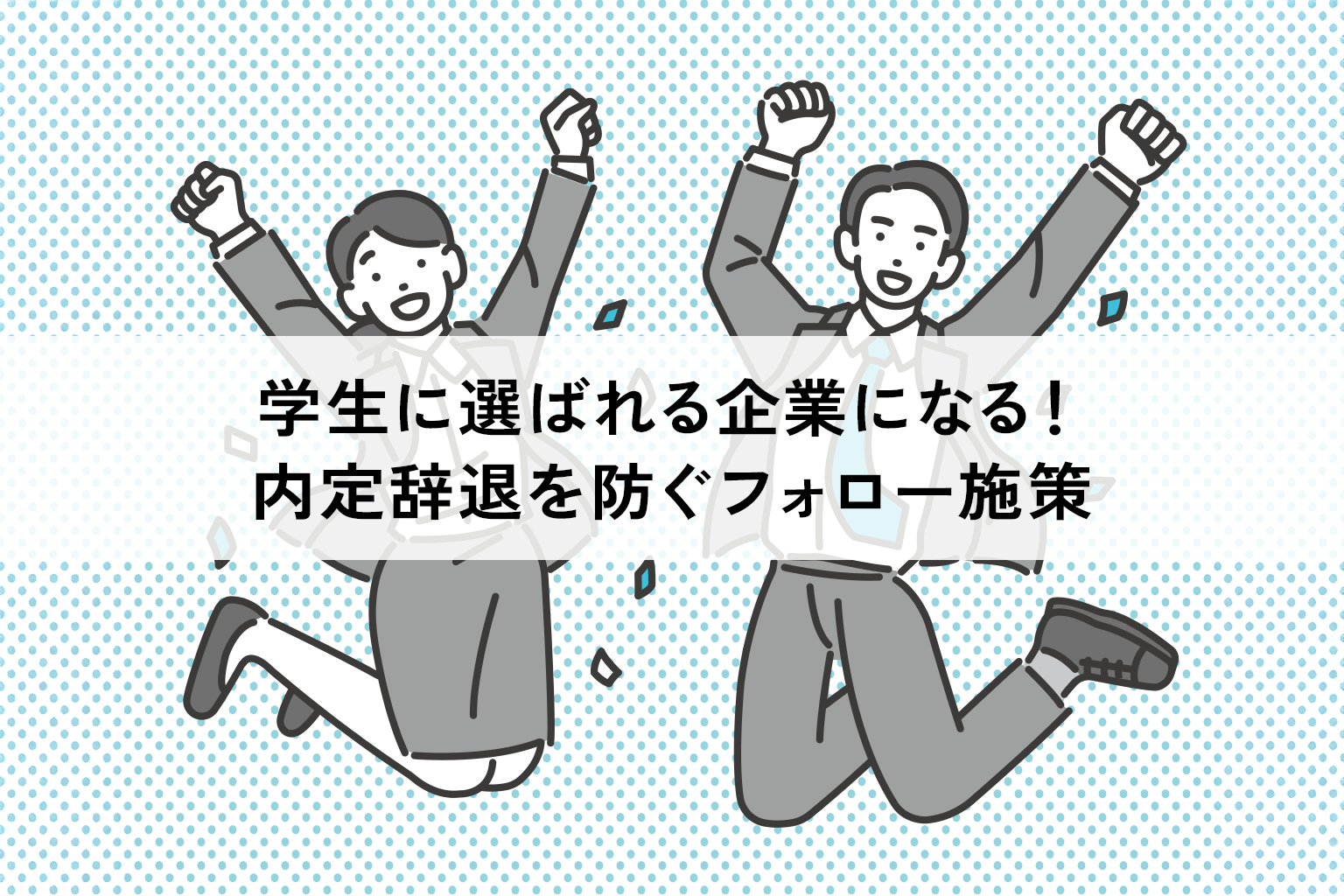“その熱意、「オワハラ」になっていませんか?”
採用活動における高い内定辞退率は、多くの企業が抱える経営課題です。 この課題を前に、多くの企業は内定者へのフォローを強化し、自社の魅力を伝えようとします。しかし、学生の引き止めに熱心になるあまり、「熱意」と「強要」の境界線が曖昧になり、過度な接触や強引な働きかけにまで及んでしまうケースが後を絶ちません。
こうした企業の行き過ぎた行為こそが、昨今SNSなどでも問題視されている「オワハラ(就活終われハラスメント)」です。
本記事では、多くの企業が陥りがちな「オワハラ」の具体的なNG行動と、それがもたらす深刻な経営リスクを解説します。さらに、候補者から真に選ばれる企業になるための新常識として、候補者体験を高める具体的な防止策までを分かりやすく紹介します。
関連記事:知らないでは済まされない!採用ハラスメントの具体例と企業が講じるべき防止策
オワハラとは?SNSだけに留まらない社会的な課題
この問題は、もはや単なるSNS上の話題ではなく、国も看過できない社会的な課題となっています。厚生労働省の発表によると、2024年4月からわずか5ヶ月弱で、全国の新卒応援ハローワークには54件ものオワハラに関する相談が寄せられました。これは、公的な窓口に助けを求めるという、いわば氷山の一角です。実際には、声を上げられずにいる学生がさらに多く存在することを思えば、企業側がこの問題を重く受け止める必要性がお分かりいただけるでしょう。
出典:(厚生労働省)厚生労働省におけるオワハラ防止に関する取組
現代の学生は、企業の「公正さ」や「透明性」を厳しく評価しており、強引な囲い込みは、個人の選択を尊重しない「不誠実な企業文化の表れ」と見なされ、“入社してはいけない企業”の重要な判断材料になっています。
オワハラの具体例|やってはいけないNG行動チェックリスト
オワハラの具体例をチェックする前に、まず現代の就活生の価値観を理解することが不可欠です。Z世代にとって、複数の選択肢を比較検討し、納得して入社を決めるのは合理的な行動です。
このプロセスを企業が一方的に妨害する行為は「熱意」ではなく、「自社の魅力に自信がない表れ」と見なされ、候補者の信頼を著しく損ないます。以下のリストを参考に、自社の行動が当てはまっていないかご確認ください。
- 【強要・束縛型オワハラ】
- 内定を出す代わりに、その場で他社の選考をすべて辞退するよう強要する。
- 「今、この場で内定承諾書にサインしなければ、内定はなかったことになる」と、決断を過度に急かす。
- 「誠意を見せてほしい」などと、精神論で他社選考の辞退届の提出を求める。
- 【過干渉・拘束型オワハラ】
- ほぼ毎日のように電話やメールを送り、行動を把握しようとする。
- 「研修」「先輩社員との懇親会」といった名目で、断りづらいイベントを頻繁に設定し、候補者を物理的に拘束する。
- 推薦状を提出させ、「大学や教授に迷惑がかかる」という状況を作り出し、心理的に辞退しにくくする。
- 【恫喝・精神攻撃型オワハラ】
- 内定辞退を申し出た候補者に対し、「裏切り者だ」「社会人として無責任だ」などと人格を否定する。
- 「君を採用するために、どれだけのコストがかかったと思っているんだ」と、過度な恩着せがましい発言や脅迫めいた言動で翻意を迫る。
- オフィスに呼び出し、長時間にわたって説得(説教)を続ける。
これらの行為は、候補者の「職業選択の自由」を侵害するハラスメントであると同時に、企業の採用ブランディングを大きく毀損するリスク行為です。
オワハラがもたらす3つの深刻な経営リスク
オワハラは、短期的な内定承諾という成果と引き換えに、企業の未来を支える「評判」「採用」「定着」という経営資本を失う、極めて割に合わない行為です。具体的に3つのリスクを解説します。
リスク1:企業の評判・ブランドイメージの失墜
SNSや口コミサイトに「オワハラ企業」という投稿が一つでもなされれば、その悪評はデジタル・タトゥーとして半永久的に残り続けます。学生は企業の公式情報よりもリアルな口コミを重視するため、採用ブランディングは深刻なダメージを受け、企業の信頼性を根本から揺るがします。
リスク2:採用力の決定的な低下
悪評は未来の候補者にも確実に届きます。「オワハラ企業」という認識が広まれば、優秀で情報感度の高い学生ほど応募を避け、採用の母集団は質・量ともに低下します。結果として、企業の成長を支える人材獲得が困難になります。
リスク3:早期離職によるコストの増大
たとえオワハラによって入社に至ったとしても、その社員は「無理やり入社させられた」という不信感を抱えています。エンゲージメントは低く、早期離職につながる可能性が極めて高くなります。これは、採用と教育にかけたコストが無駄になるだけでなく、組織全体の士気低下にもつながる大きな問題です。
【実践編】「囲い込み」から「ファン創り」へ。候補者体験(CX)を高める新常識
オワハラに頼らず内定辞退を防ぐには、候補者を強引に「囲い込む」のではなく、自社の魅力で惹きつけ「ファンにする」という発想の転換が不可欠です。ここでは、その中核となる「候補者体験(Candidate Experience)」を高めるための、3つの具体的なアプローチを解説します。
① 鉄則は「心理的安全性」の提供
内定者フォローの出発点は、候補者に「この会社は自分を尊重してくれる」という安心感、すなわち「心理的安全性」を提供することです。
回答期限には十分な猶予を設ける
「納得いくまで考え、ご自身のキャリアにとって最善の選択をしてください」というスタンスを明確に伝えます。これは、自社の魅力に対する自信の表れでもあります。
相談相手になることを申し出る
「何か迷っていること、不安なことがあれば、いつでも相談してください。他社さんと比較した上での疑問でも構いません」と伝え、候補者の意思決定をサポートする誠実なパートナーとしての関係を築きます。
② グレーゾーン質問の言い換えテクニック
入社意欲を確認したい気持ちは分かりますが、一歩間違えればオワハラになりかねない質問も存在します。ここでは、候補者との信頼関係を深めるポジティブな言い換えテクニックを紹介します。
【NG質問】:「うちが第一志望ですか?」
候補者に「はい」と答えさせる圧力をかけ、嘘をつかせる可能性があります。
【OK質問】:「〇〇さんの就職活動の軸を改めてお伺いし、その中で当社がどのように貢献できるか、一緒に考えさせていただけますか?」
対等な立場で、候補者のキャリアを一緒に考えるパートナーとしての姿勢を示せます。
【NG質問】:「正直、他社の選考状況はどうなっていますか?」
探られている、試されているという不信感を与えかねません。
【OK質問】:「差し支えなければ、他にはどのような業界や企業を視野に入れているか教えていただけますか?〇〇さんのキャリアプランをより深く理解する上で、参考にさせてください。」
質問の意図を明確に伝え、あくまで「あなたを理解するため」という誠実な目的を伝えられます。
③ 不安を「解消」し、期待を「醸成」する具体的フォロー術
候補者との信頼関係を築いた上で、次に行うべきは、具体的なアクションを通じて入社への意欲を高めてもらうことです。重要なのは、候補者の時間を尊重し、「価値ある情報」と「自然な交流」を提供することです。
リアルな情報を提供する
良い面だけでなく、会社の課題や「入社後にぶつかるかもしれない壁」についても正直に話すことで、透明性の高い企業文化を伝え、信頼を深めます。
年の近い先輩社員と話す機会を設ける
人事には聞きづらいリアルな働き方や悩みを相談できる場を用意します。あくまで参加は任意とし、オンラインでのカジュアルな座談会などが効果的です。
内定者同士のつながりを作る
参加必須ではないオンライン懇親会などを企画し、同期となる仲間との関係構築をサポートします。「この仲間たちと一緒に働きたい」という気持ちは、強力な入社動機になります。
まとめ:真のゴールは「内定承諾」ではなく「入社後の活躍」である
本記事では、オワハラのリスクと、候補者体験を高めることで内定辞退を防ぐアプローチを解説しました。強引なオワハラによって得た内定承諾は、企業にとって見せかけの成功でしかありません。なぜならその内定承諾は、入社後のミスマッチや早期離職といった、将来的な損失に直結するからです。
採用活動の真のゴールは、内定承諾書にサインさせることではありません。候補者が心から「この会社で働きたい」と納得して入社を決め、入社後に生き生きと活躍してくれることにあります。
候補者を尊重し、最高の候補者体験を提供することは、優れた採用ブランディングそのものです。情報が瞬時に共有される現代において、この誠実な姿勢こそが企業の持続的成長を支える、最も効果的な採用戦略と言えるでしょう。