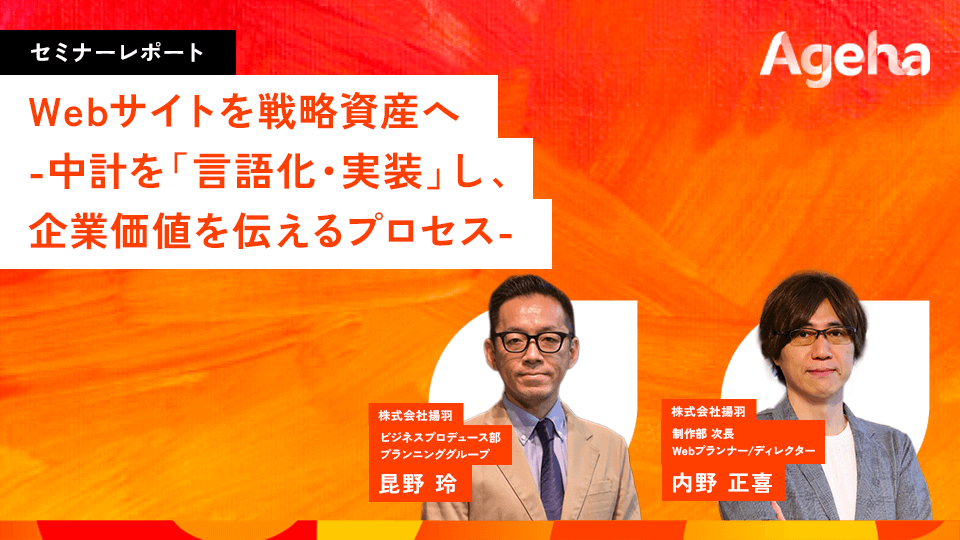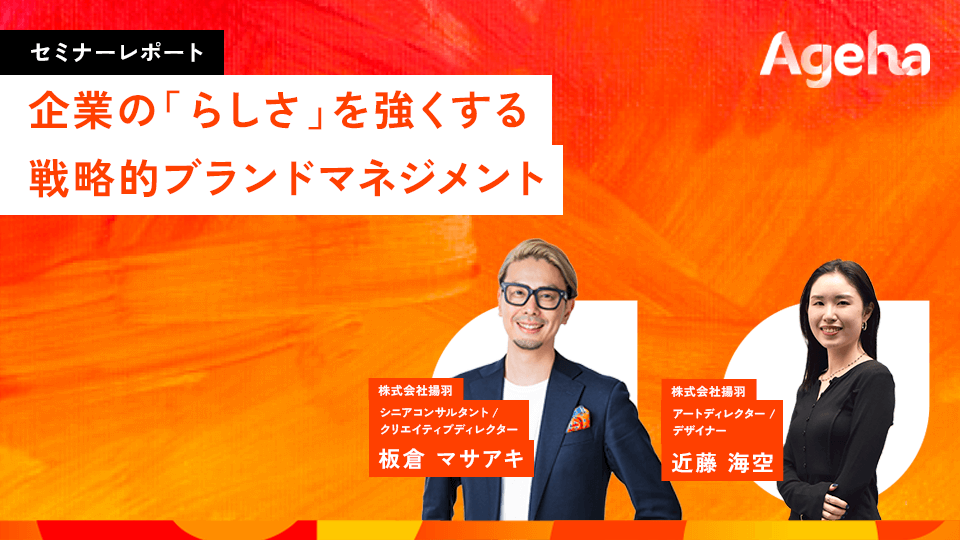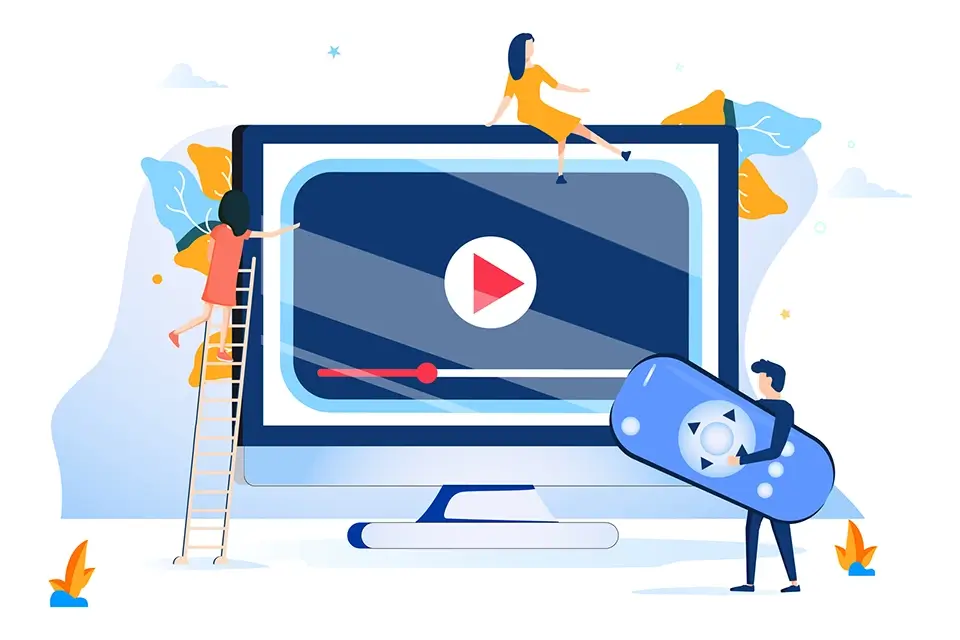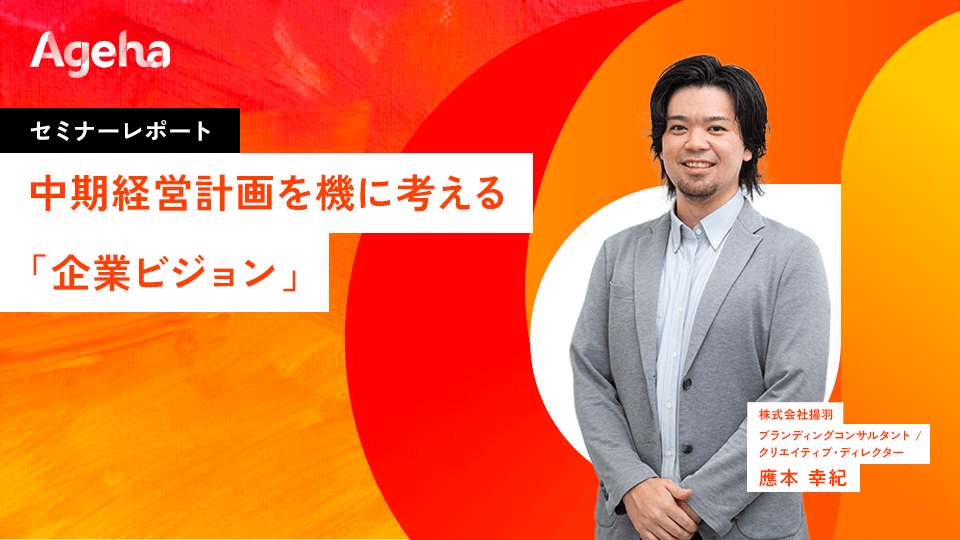「AIの回答に、自社サイトが引用されているのだろうか?」
「最近、検索流入が明らかに減っている」
こうした声を、企業の担当者の方から伺う機会が増えてきました。
そこで注目を集めているのが「LLMO(Large Language Model Optimization、大規模言語モデル最適化)」です。国内では「LLMO対策」と呼ばれることが多い一方で、GEOやAIOなどの呼称も併存しており、まだ定まっていない状況です。
LLMOとは、ChatGPTやPerplexity、GoogleのAI OverviewやAI Modeといった生成AIが検索結果や回答を生成する際に、自社のコンテンツが引用・参照されたり、ブランドが正しく言及されることを目的とした最適化手法です。また、生成AIに自社やブランドを適切に学習させるための取り組みもその範疇に含まれます。
本記事では、LLMOの基本概念からSEOとの違い、実践的な施策の進め方、さらに生成AI時代におけるマーケティング構造の変化までを、当社のナレッジも交えて網羅的に解説します。
関連記事はこちら:AIOとは?AI検索最適化の基本から対策方法まで徹底解説
生成AIによる検索体験の変化
いま、ユーザーの情報収集行動はかつてない転換点を迎えています。検索エンジンにキーワードを入力するのではなく、ChatGPTやGeminiといった生成AIに自然な言葉で質問を投げかけて回答を得るユーザーが急増しています。さらに2025年5月20日にはGoogleが新機能「AI Mode」を発表し、9月9日には日本語版の提供も始まりました。こうした動きからも分かるように、生成AIが検索体験の中心に組み込まれる流れは一層加速しています。
この変化の中で、自社のWebコンテンツが生成AIの回答に引用・参照されるかどうかは、従来のSEOとは異なる新たな競争軸となりつつあります。
このように、生成AIが検索体験の中心になる時代が到来しています。実際に、企業担当者の85.3%が「生成AIにより企業認知の方法が変化した」と回答しており(2025年8月調査)、この変化への対応は必要不可欠です。
この新たな競争軸で勝ち抜くために必要な戦略こそ、次章より解説する「LLMO」です。
LLMOとは?基本概念を理解する
LLMOの定義
LLMOとは、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexityなどの生成AIが回答を生成する際に、自社のWebコンテンツを優先的に引用・参照してもらうための最適化手法です。
従来のSEOが検索エンジンアルゴリズムへの最適化だったのに対し、LLMOは生成AIの情報処理プロセスに特化した、これまでとは異なる新しいアプローチです。AIが「この情報は信頼できる」と判断し、回答に活用してもらうことを目指します。
LLMOとAIOの関係
LLMOは、より広範囲なAIO(AI Optimization:AI検索最適化)戦略の中核を成します。
- LLMO:大規模言語モデルへの最適化
- AI Overview対策:Google AI Overviewでの露出最大化
- 音声AI対策:音声検索・AIアシスタント対応
なぜ今LLMOが注目されているのか?
生成AI時代のマーケティング変革
2022年のChatGPT登場以降、マーケティング環境は劇的に変化しました。
| 変化の要素 | 従来(2022年以前) | 現在(2024年以降) |
| 情報収集方法 | キーワード検索→サイト閲覧 | AI対話→即座の回答取得 |
| ユーザー期待 | 関連サイトのリスト表示 | 要約された具体的回答 |
| マーケティング戦略 | SEO対策が中心 | SEO+LLMO対策 |
| 競争軸 | 検索上位競争 | AI引用獲得競争 |
「ゼロクリック検索」の脅威
Ahrefsの最新調査では、AI Overview表示時のクリック率が平均34.5%低下することが判明。ユーザーがAIの回答だけで満足し、元のWebサイトを訪問しない「ゼロクリック検索」が急増しています。
生成AIによる情報収集が主流となる中、AI最適化を怠る企業は「AIに選ばれない=存在しない」企業として、ブランド認知と顧客獲得の機会を競合に奪われるリスクが急激に高まっています。
LLMOと従来SEOの決定的な違い
従来のSEOとLLMOの間にある、根本的な違いを理解しましょう。
| 比較項目 | 従来のSEO | LLMO |
| 最適化対象 | Google検索アルゴリズム | 生成AI(ChatGPT等) |
| 目指すゴール | 検索結果上位表示 | AI回答への引用獲得 |
| ユーザー行動 | 検索→クリック→閲覧 | 質問→AI回答で完結 |
| 成功指標 | 検索順位・流入数 | AI引用頻度・ブランド認知 |
| 競争相手 | 同業他社サイト | あらゆるWeb情報 |
LLMO重要要素トップ5
SEOとLLMOは敵対関係ではありません。むしろ相互補完の関係にあり、両方に取り組むことで最大限の効果を発揮します。検索上位サイトがAIに引用されやすい傾向があるため、SEOの基盤の上にLLMO対策を積み重ねることが成功の鍵です。
- 構造化データの実装:AIが理解しやすい情報構造を提供
- FAQ形式コンテンツ:AIが好む質問-回答形式での情報提供
- 一次情報の発信:独自調査・データの積極的な公開
- E-E-A-T強化:専門性・権威性・信頼性の証明
- 簡潔で明確な文章:AIが処理しやすい文章構造
AIがあなたのサイトを選ぶ仕組み
生成AIの情報選択プロセス
生成AIは膨大なWeb情報の中から、どのように回答に使用する情報を選んでいるのでしょうか?そのプロセスを理解することが、LLMO成功の第一歩です。
- 質問分析:ユーザーの真の意図を解析
- 情報収集:関連性の高い情報源を幅広く収集
- 信頼性評価:各情報源の権威性・正確性を判定
- 内容統合:最適な情報を組み合わせて回答を構築
AIが「信頼できる」と判断する条件
AIが情報を選択する際の基準として、主に以下の3点が挙げられます。
- 権威性:専門機関・有名企業・実績のあるサイト
- 具体性:数値データ・事例・一次情報の豊富さ
- 構造性:整理された情報・明確な見出し構造
「コンテキストウィンドウ」の重要性
AIが一度に処理できる情報量には限界があります。この制限を「コンテキストウィンドウ」と呼び、効率的な情報提供が求められます。
(参考情報)主要AIの処理能力:
|
LLMO対策の具体的手法
【即効性】テクニカル対策
llms.txtファイルの設置
AIにサイトの概要を効率的に伝える新標準「llms.txt」を設置しましょう。robots.txtのAI版として機能します。
| # llms.txt設置例
# 株式会社揚羽 # デジタルマーケティング・ブランド戦略 ## 会社情報 ## 主要ページ |
構造化データの実装
AIが情報を正確に理解できるよう、Schema.orgマークアップを実装。
- Article:記事情報の構造化
- FAQPage:Q&A形式コンテンツ
- Organization:企業情報の明示
サイト高速化
AIクローラーも高速サイトを優先します。
- ページ速度:Core Web Vitals改善
- 画像最適化:WebP形式採用
- 不要コードの削減
【持続性】コンテンツ対策
FAQ形式の徹底活用
AIが最も好む「質問→回答」形式でコンテンツを構成します。効果的なFAQ作成法は以下の通りです。
- ユーザーが実際に検索する表現を質問に使用
- 回答は200-300字で簡潔にまとめる
- 専門用語は必ず解説を併記
- 関連質問を複数設定して網羅性を確保
一次情報の継続発信
AIは独自性の高い情報を最優先で引用します。
- 独自調査:業界動向・ユーザー行動分析
- 専門家の見解:インタビュー・対談記事
- 実証データ:効果測定・比較検証結果
- 事例研究:具体的な成功・失敗体験
E-E-A-T強化戦略
Google品質評価基準であるE-E-A-Tは、LLMOでも重要な評価軸です。
| 要素 | 対策例 | 期待効果 |
| Experience(経験) | 実プロジェクト事例・体験談 | 実体験に基づく信頼性 |
| Expertise(専門性) | 深い専門知識・技術解説 | 専門分野での優先引用 |
| Authoritativeness(権威性) | メディア掲載・業界認知 | 情報源としての格上げ |
| Trustworthiness(信頼性) | 情報更新・出典明記 | 長期的な引用継続 |
LLMO効果測定の方法
成果を可視化する3つの指標
AI引用回数の追跡
主要AIサービスでの自社引用状況を定期的に確認することで、追加の対策を講じる必要性があるか判断します。
- 手動監視:ChatGPT、Gemini、Perplexityでの引用確認
- 専用ツール:Otterly.aiなどAI引用監視サービス
- 競合比較:同業他社との引用頻度比較
AI経由流入の測定
Google Analytics 4でAI経由のサイト流入を識別し、施策の効果を検証します。
主要AI参照元:
|
指名検索数の変化
AI露出によるブランド認知向上を測定するため、施策前後での検索ボリュームを確認します。
- Google Search Console:自社名検索数の推移
- Google Trends:ブランド検索トレンド分析
- SNS言及:ソーシャルメディアでの言及数変化
LLMO成功への実践ステップ
段階別実装ロードマップ
【第1段階】基盤整備(1-2ヶ月)
- llms.txtファイル作成・設置
- 既存コンテンツの構造化データ実装
- サイト速度・技術的改善
【第2段階】コンテンツ強化(2-4ヶ月)
- FAQ形式コンテンツの充実
- 一次情報・独自データの発信開始
- 専門性を示すコンテンツ拡充
【第3段階】継続最適化(4ヶ月~)
- AI引用状況の定期監視
- 効果測定に基づく改善施策
- 業界最新動向への対応
【実証済み】株式会社揚羽の成果事例
自社オウンドメディア「Ageha MAGAZINE」での実証実験結果(2025年)
- 検索表示回数 130%向上:メディア全体での検索エンジン露出が大幅増加
- 「ブランディング」キーワード大幅上昇:22位→2位へ順位向上し流入増に貢献
- 生成AI引用率向上:主要キーワードでのAI回答参照率が改善し問い合わせ増加
- 統合的アプローチの効果:LLMO×SEO×ブランディングの相乗効果を実証
LLMOの未来とマーケティング展望
2025年以降のAI検索進化
AI検索技術は急速に進歩しており、以下の変化が予測されます。
- リアルタイム情報更新:最新情報の即座反映
- 個人最適化の強化:ユーザー履歴基づくパーソナライズ
- マルチモーダル検索:テキスト・画像・音声統合
- 対話の高度化:複数回の質問による深掘り検索
LLMO成功に向けて企業担当者が考慮すべきポイント
AI時代のブランディング促進のため、企業担当者が考慮しておくべきポイントは、大きく以下の4つが挙げられます。
- AI技術の基礎理解:生成AIの仕組み・特性把握
- 構造化思考力:情報整理・体系化スキル
- データ分析力:効果測定・改善立案能力
- コンテンツ企画力:独自情報の継続創出
まとめ:今すぐ始めるLLMO対策
生成AI時代の到来により、マーケティング戦略は根本的な変革を迫られています。LLMOは単なる技術対策ではなく、AI時代を勝ち抜くための必須戦略です。
いまから始める基本施策
- llms.txtファイル設置:AIにサイト概要を効率的に伝達
- FAQ形式コンテンツ充実:AIが好む質問-回答形式の拡充
- 構造化データ実装:AI理解を促進する情報マークアップ
- 一次情報発信開始:独自性の高いコンテンツ制作
LLMOで目指すゴール
「AIに選ばれるブランド」として、ユーザーがAIに質問した際に、真っ先に引用・紹介される存在を目指しましょう。これがAI時代のブランド価値向上と競争優位性確立の鍵となります。
株式会社揚羽のAI最適化支援サービス
株式会社揚羽では「AI最適化型デジタルマーケティング支援サービス」を2025年9月より本格提供開始します。
有志メンバーによる社内AIプロジェクトを立ち上げ、LLMO対策についてディスカッションや検証を重ねてきました。AI検索時代では、SEOだけではなくLLMO、AIOに取り組むことが、競争優位性を確立するための新たな取り組みとして重要です。
こうした検証結果からの知見を踏まえ、効果を確認済みの手法で、企業様の「AIに選ばれるブランド」への変革をサポートいたします。
- 【調査・分析】:AI検索での自社ブランド参照状況、競合比較、構造化データ評価
- 【戦略策定】:生成AI対応コンテンツ形式、ブランドエンティティ強化を含む統合戦略
- 【施策実行】:AI対応コンテンツ企画・制作、UX改善をワンストップ提供
- 【検証・改善】:AI引用数、生成AI経由流入数をKPIとした継続改善
ぜひご興味がございましたら、気軽にお問い合わせください。