“人財育成”を企業経営の第一に据える
大和ハウス工業株式会社は、1955年創業でハウスメーカーとゼネコン双方の顔を持ち、生活インフラを支える総合的な建設事業を展開する企業です。「建築の工業化」を基本理念に、戸建住宅、賃貸住宅、分譲マンション、商業施設、物流施設、医療・介護施設、環境エネルギーなど、幅広い領域でサービスを展開しています。2024年度には、過去最高の売上高を達成。2026年度まで5カ年の第7次中期経営計画を1年前倒しするなど、業績も好調に推移しています。
同社は「事業を通じて人を育てる」という社是を掲げ、人財の価値向上が企業価値の源泉であると捉えています。創業以来、人財の成長を第一に考えた経営を行ってきました。その中で、2023年には「人財育成ポリシー」を策定し、「Keep Learning, Growing, and Dreaming.」(学び続けよう、成長し続けよう、そして、夢を追い続けよう)をコンセプトに、従業員が真のプロフェッショナル人財として成長するため「機会、仲間、職場」という3つの基盤づくりを実践。複線的な成長機会の提供を通じて、従業員の自律的かつ持続的なキャリア形成を支援しています。
創業70周年にあたる2025年度は、5兆6000億円の売上高を計画しており、創業100周年の2055年には、10兆円という目標を立てています。そこに向けては、従業員一人ひとりの見える風景が変化し、ビジネスモデルも変える必要があると、大和ハウス工業の松本由香子氏(本社経営戦略本部 人事部 採用・人財開発グループ長)は語ります。「社是の『事業を通じて人を育てる』ことが、どのようなことなのかを明確にするため、人財育成ポリシーを策定しました。ただポリシーは作りましたが、社内にインパクトを持って公開できていませんでした」(松本氏)。
「日常的な学びが当たり前」になることを目指す
そこで、大和ハウス工業では人財育成ポリシーとともに、数年かけて導入を準備してきたLMS(Learning Management System:学習管理システム)の運用を開始。ポリシーに基づいて、従業員が自律的、持続的に学べるような環境を整備しました。

LMSのウェルカムページ
このLMSは、eラーニングを含む学習活動を管理するシステムで、教材の配信や学習進捗の管理、成績表示、アンケート、レポート機能などを搭載しています。「1万6000人の従業員にLMSを浸透させ、日々の業務の中で従業員が自然に使うものにしたいと考えました。それによって、学ぶことが日常の当たり前になれば、一人ひとりのキャリアや人生が豊かになる企業文化が醸成されるのではないでしょうか」(松本氏)。
同社では、こうした社内風土を実現するにはLMSの存在を従業員に伝え、利用したいと思えるような情報発信が必要だと考えました。そして、そのための社内向けインナーブランディングを行うパートナーとして選んだのが当社でした。導入したLMS「コーナーストーン」のウェルカムページを、当社が数多く手がけている実績があった点が、選定の大きな理由だったと大和ハウス工業の小山内翔太氏(本社経営戦略本部 人事部 採用・人財開発グループ 主任)は明かします。
「揚羽さんが制作した事例を見て、直感的に私たちのニーズに合っていると感じました。私たちが期待しているように、従業員に向けた情報発信の大きな力になると考えたのです。加えて、LMSの公開まで、制作期間は3カ月しかありません。間に合うかどうかを危惧しましたが、『大丈夫』と返事をいただき、揚羽さんに依頼しました」(小山内氏)。
従業員が集う学びの場として「&D Campus」と命名
このプロジェクトでは、「&D Campas(アンドディーキャンパス)」というプラットフォーム名とロゴ、人財育成ポリシーのキャッチコピーにあったキービジュアルなどを作成しました。「最もよかったのは、皆が集う学びの場として『&D Campus』というプラットフォーム名を付けられたことです。人財育成ポリシーのコンセプトはありましたが、従業員が日常的に触れるのはLMSなので、そのネーミングはとても重要です。揚羽さんからは様々な意味が込められた『&D』という提案をいただいたのが素晴らしかったですね。それに私たちが、すべての従業員が仲間とともに学び、成長し、夢を追い続ける、そのための『交流の場』を意味する『Campus』を加えて、従業員にとっても非常に愛着が湧くネーミングになりました」(松本氏)。
たくさんの想いが込められた人材育成ポリシーのビジュアル化に向け、中身をかみ砕き、深く理解する過程では時に難しい面もあったと株式会社揚羽の小島愛美(ブランドマーケティング部 ブランドマーケティング2グループ)は説明します。「初回の打ち合わせ以降、何度も時間をいただき、人財育成ポリシーや社内にある概念を理解するため、繰り返しコミュニケーションを取りました。そのおかげで、イメージを制作メンバーにもきちんと伝達でき、腹落ち感のある提案ができたと思います。対応してくれた担当の皆様には、本当に感謝しています」(小島)。
プラットフォームの名称については、当初大和ハウス工業と当社で多くの案を出し合ったと株式会社揚羽の佐野崇倫(制作第1部 ディレクター3グループ マネージャー)は振り返ります。「社名から“D”という文字を使ったり、お客様の社内から出た意見なども加味しながら、『&D Campus』という簡潔でキャッチーな名称になってよかったと思います。これに合わせる形で、ロゴやキービジュアルのデザインも統一したイメージにできました」(佐野)。

「&D Campas(アンドディーキャンパス)」のロゴ
ロゴやキービジュアルのデザインは、未来感と期待感を軸に作成しましたが、抽象的すぎると、期待感だけが先行して何のサイトかわからなくなるという懸念があると、株式会社揚羽の茅野有夢実(制作第2部 デザイナー2グループ リーダー)は話します。「逆に、学習や学びなどに寄りすぎると固い印象になってしまう可能性があります。その中で、自分で考えるだけでなく、関係者の意見を聞きながらアウトプットしていきました。最終的には未来感を感じつつ、具体的な学びを表現するデザインにできて、とても満足しています」(茅野)。
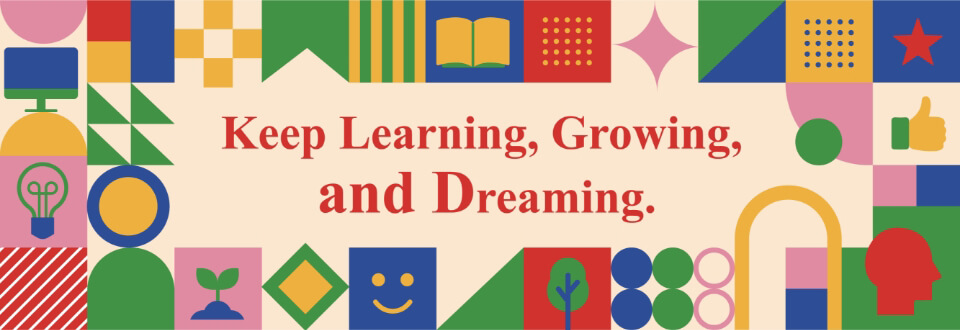
キービジュアル
運用開始数カ月で従業員の9割が利用、自律学習も着実に拡大
2024年7月、「&D Campus」は計画通り、稼働を開始しました。スタート段階でのログイン数は約6000人、自律学習のための外部コンテンツの受講は660人ほどで、1万6000人の従業員の内、実際に学習活動をしたのは5%に満たなかったといいます。その後、eラーニングなどを「&D Campus」からアクセスするようにしたこともあり、9月のログイン数は1万4000人と順調に伸びていきました。
その後も、ログイン数は同じ水準を維持していて、9割近くの従業員が利用しています。一方、2024年10月に昇格の要件に自律学習コンテンツの閲覧を入れたことから、受講者数も8月の約1000人から10月には2800人を超えました。「受講者数は徐々に増えており、2025年3月末時点で、自律学習コンテンツを一度でも受講したことがある従業員は8000人に達しました。2025年4月から6月までの3カ月間でもさらに2000人以上増えおり、合計で1万人を突破するほどになり、『&D Campus』を利用した自律学習が着実に浸透しています」(小山内氏)。
こうした伸びの背景には昇格制度と絡めたプログラムを用意したことだけでなく、社外のコンテンツも含めて幅広いジャンルで、9000近いコンテンツを社内教育でも積極的に利用する部門が増えてきたことがあるといいます。「教育や研修に関するポータルサイトなど、すべての窓口を『&D Campus』にしています。さらに、『&D Campus』を使って勉強する従業員のメッセージなどあらゆる階層の動画を載せて、このLMSから学ぶ世界が広がっているという環境を作っています。そうした中で、従業員のほとんどが『&D Campus』を訪れているのは本当に嬉しいと感じていて、これからもこの状況をさらに広げていく考えです」(松本氏)。
大和ハウス工業では、「&D Campus」の運用を通じて、企業としての学びに対する熱意やイメージを従業員に伝え、楽しく学び続けられる土壌醸成の大きなステップを踏み出せたと考えています。その上で、今後、人事施策のエンゲージメント向上と絡めた仕組みや、従業員同士のコミュニティ形成、従業員一人ひとりに最適化された学習プランなど、様々な実施施策を検討していく構えです。






